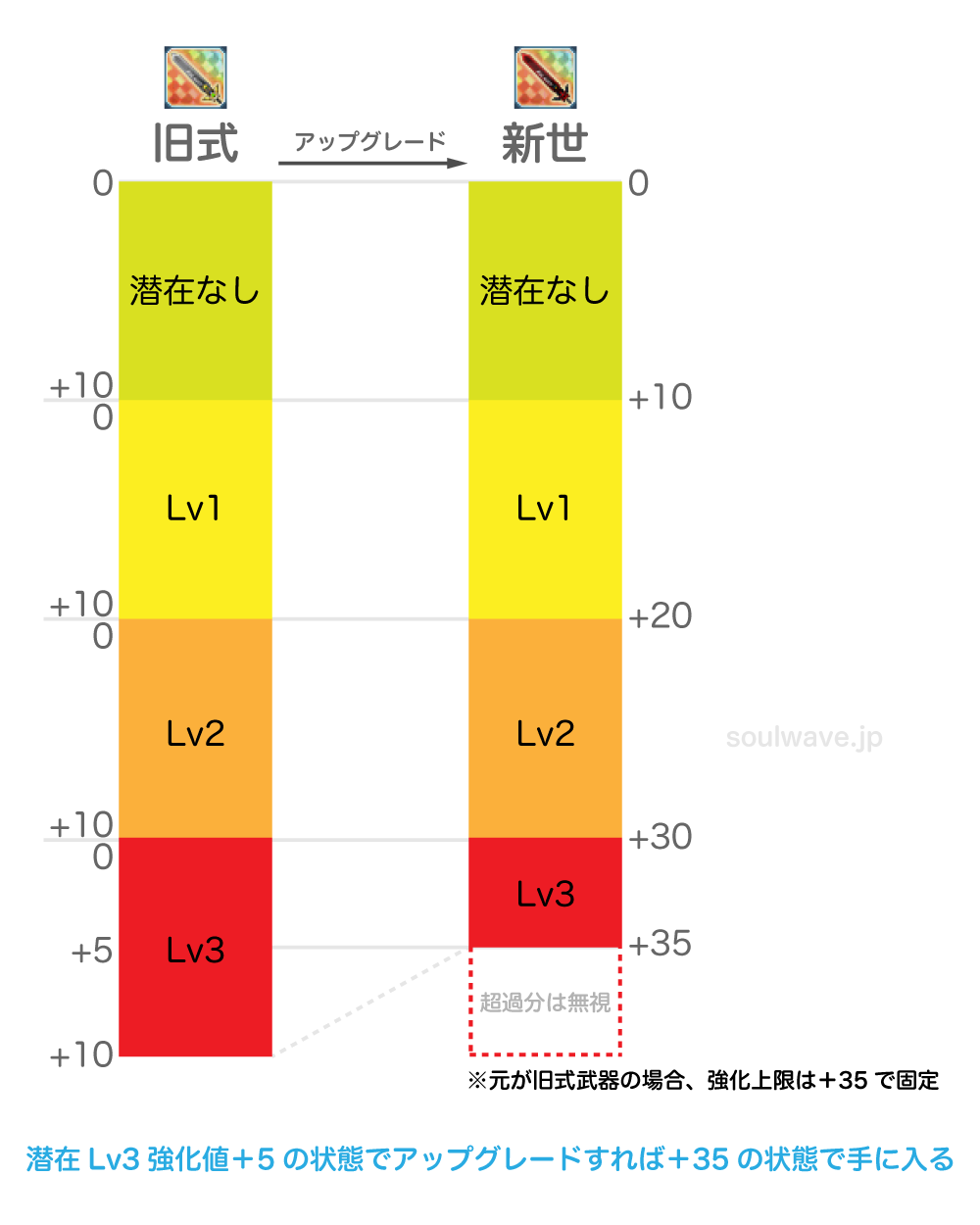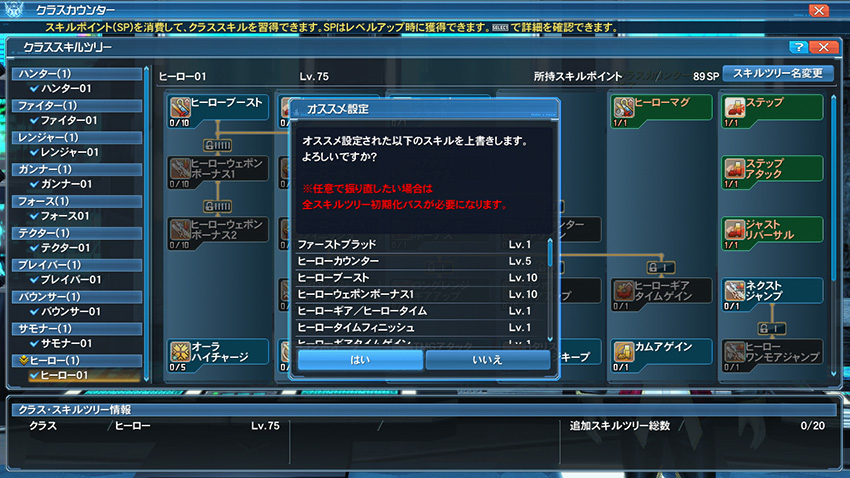先手を打ったのはスタークォーツだった。相手との間合いはおよそ十歩。既に運動能力強化テクニックであるシフタを自分に付与していた彼女はその距離を1歩で詰めた。
体重と突進の加速を重ねた刺突。その刃が到達しようとする直前にアマサギが動いた。担いだ剣を振り下ろす一撃は、後手であるにも関わらずスタークォーツの攻撃よりも先に命中しようとしていた。
スタークォーツはとっさに床を蹴って横に避けようとする。だが、アマサギの太刀筋は垂直に曲がって追いかけてくる。これ以上はあえて体勢を崩して倒れながら避ける他無かった。
視界の隅で二の太刀を振り下ろそうとするアマサギの姿が見える。スタークォーツは跳ね上がるように起き、自分の剣で受け止める。
「まずは皆伝と認めるだけの力を持っているようですね。ですが、この白のセイバーを持つ剣士は更にその先へ行かなければなりません」
「言われるまでもありませんよ」
強気に振る舞うが、内心では開祖の技に畏れを抱いていた。相手の攻撃に合わせて対応する「後の先」を極め、後手を先手に変える剣士という伝説を持つアマサギ流の開祖。その力を見くびっていたわけではないが、実際はスタークォーツの想像以上であった。
しかし、完全な弱気になっているわけでもない。皆伝を認められた後はアークスの戦闘員として実戦の中で研鑽に励んできたのだ。その力を開祖に示す。そう考えてスタークォーツは畏れを闘志に変えた。
二人の女剣士は互いに離れて間合いを取る。
アマサギは剣が届かない間合いであるにも関わらず、攻撃の構えを取る。テクニックを使った技を繰り出すのは明白だった。
白のセイバーに炎が宿ると、その炎は細長く伸びてスタークォーツへ襲いかかる。炎の鞭で間合いの外から相手を捉える【ギ・フォイエ:大蛇の型】だ。
遠間から攻撃をスタークォーツが剣で受け止めると、炎の鞭はそのまま刀身に巻き付く。
危険な状態だ。スタークォーツがそう感じたと同時にアマサギが次の行動に移る。
「せいっ!」
アマサギが渾身の力を込めて、炎の鞭を引っ張る。剣を奪うためか、あるいは相手の姿勢を崩すためか。不用意に抵抗するのは危険と判断したスタークォーツは、自ら引っ張られる方向に向かって跳ぶ。
スタークォーツは空中で【ラ・ザン:螺旋の型】を使う。刀身の周囲に生み出さした円錐状の竜巻で巻きついた炎の鞭をかき消し、そのままアマサギへ突き刺そうとすると、彼女もまた【ラ・ザン:螺旋の型】を使って来た。
小さな二つの円錐竜巻がぶつかりあう。
「むぅ、なんという暴風か」
竜巻がぶつかりあった影響は、離れた場所で戦いを見守っているハヤブサにまで及んでいた。今やこの空間全体で暴風が吹き荒れている。
スタークォーツもアマサギも円錐竜巻の回転数を上げて相手を押し切ろうとするが、どちらも相手を圧倒することが出来ず、回転数に比例して増大する反発力に耐えきれずに二人の剣は遠くへと弾き飛ばされてしまった。
これが他流における剣士同士の戦いならば、二人は弾かれた剣を回収しに走るだろう。しかし剣士にしてテクニック使いであるアマサギ流同士の戦いは、たとえ徒手空拳であっても剣戟は続く。
どちらも弾き飛ばされた剣には目もくれず、次なる攻撃に移る。スタークォーツとアマサギの二人が使った技は【ギ・グランツ:飛剣の型】だ。空中にフォトンの結晶で出来た剣を生成し、それを矢のように射出する。
結晶剣は空中で激しく打ち合う。そこにすかさず、アマサギは2本めの結晶剣を生み出して発射し、スタークォーツもそれに対応して新しい結晶剣を生成する。それは3本目、4本目と続き、5本目で最後となる。
合計10本の結晶剣が激しく打ち合う。スタークォーツもアマサギもその場から一歩も動かずに結晶剣の制御に集中する。もし僅かでも集中を途切れさせてしまえば、相手が操る結晶剣が一斉に自分へと襲いかかる。
この膠着状態を打開するにはどうすればよいか、スタークォーツは考えた。何か一つ、相手よりも優位といえる何かを手にする必要がある。結晶剣を更に増やすべきか? だが、結晶剣を追加するだけのフォトンは残されていない。【ギ・グランツ:飛剣の型】を解除し【イル・ゾンデ:嵐の型】で一気に勝負をつけるべきか? 同じ技は開祖であるアマサギも使える。相手よりも素早く動けるという優位点は得られないだろう。
相手よりも優位となるために引き出す「何か」を今のスタークォーツは持っていなかった。
ではこのまま膠着状態を維持し、相手が根負けするまでも待つか? そのような剣士を白のセイバーに相応しいをアマサギは認めないだろうし、スタークォーツ自身もまた認めない。
勝つために必要となる「何か」は一体何処にあるのか。結晶剣の打ち合いの最中でスタークォーツは「それ」をついに見つけた。「それ」を手に入れるたには賭けに出る必要がある。そうしなければ勝てないだろう。
何かを賭けるとき、人は必ず決断する。だが、スタークォーツに決断など必要なかった。決断とは「それを行うべきか否か」を考えた上で、すなわち迷いの先に行われるものである。スタークォーツはためらうこと無く賭けに出た。
瞳に強い闘志が宿る。
スタークォーツはアマサギに向かって駆けだした。
アマサギの結晶剣が襲いかかる。スタークォーツは自分の結晶剣で防御するが、それは4本までであった。残る一本は攻撃に使った。
一直線に飛ぶ結晶剣をアマサギは体を僅かに傾けただけで回避する。その直後、防御しなかったアマサギ側の最後の1本がスタークォーツへと襲いかかる。
飛来する結晶剣をスタークォーツは紙一重で回避すると同時に、柄を握って奪い取った。
「なんと!」
その瞬間を見たアマサギに初めて驚きの表情が現れる。
逃れようとする結晶剣を両手でつかみ、力づくで従えたスタークォーツは、その刃をアマサギめがけて振り下ろした。
無手の状態では防御することも出来ない。勝利を確信たスタークォーツだが、アマサギは唐竹割りの一撃を両手で挟み込む形で受け止めた。
そう! 白刃取りである!
一瞬の間。極度に緊張した精神では時間が止まったかと錯覚するほどの瞬間の後、アマサギは穏やかに言った。
「お見事。あなたほどの剣士ならば安心して白のセイバーを任せることができるでしょう」
スタークォーツの手から結晶剣が消える。作った本人であるアマサギが技を解除したためだ。
アマサギは床に落ちたままだった白のセイバーを拾い上げ、それをスタークォーツへと渡す。
「これが、白のセイバー……」
初めて目にしたときから尋常ならざる力を宿している思っていたが、いざこうして柄を握ってみるとそれがより確実に伝わってくる。 白のセイバーは長年アマサギとともに戦ってきたのだろう。それによってこの剣には魂のようなものが宿っていると確信を持って感じ取れる。もはやこれは純然たる科学力によって作られた試作品の道具ではない。悪逆の徒を討ち滅ぼすための聖なる剣となっている。
ふと、アマサギの視線に気がつく。白のセイバーを見るその眼差しは、子の独り立ちを見届けようとする一抹の寂しさを抱えた母親のようであった。
「これより、私は一つの技を教えます。アマサギ流最後の奥義である【グランツ:破邪の型】。白のセイバーの機能を完全に発揮するために私が編み出した、黒のセイバーを討ち取るための技です。いつ黒のセイバーが動き出すかわからない状況です。今すぐに奥義の伝授を初めます」
「見事だったぞ、スタークォーツ。私の門下生から白のセイバーの後継者が現れたことを誇りに思う。お前ならば必ず奥義を習得できるだろう」
「ハヤブサ師範……」
スタークォーツは胸に熱いものが宿るのを感じた。アマサギ流の道場の門を叩いたときはこうなることは少しも考えつかなかった。
事故による重傷によって体を機械化し、キャストとなったスタークォーツは生身の肉体の喪失感からくるストレスに悩まされていた。医者から何か打ち込めるものがあると良いと進められ、体を動かしていれば喪失感も忘れるだろ言うと思ってアマサギ流に入門した。
性に合っていたのだろう。喪失感を忘れるために必死で修練をするうちに、自然とキャストの体が馴染んでいった。それだけでなく、自分に剣とテクニックの資質があるということがわかり、アークスの戦闘員という天職も得た。肉体を失う原因となった事故を良かったと認めるつもりはないが、最悪にならなかったことに限っては幸いであった。
これが定められた運命なのか、あるいは偶然の積み重ねによって生まれた結果なのかはわからないし、どちらが「正」であってもかまわない。自分はただ、自らが培ってきた力と信頼されて授かった力を、良心を持って振るうのみ。
他者を踏みにじる暴力を求めたヴィーラスと悪心を呼び起こす黒のセイバーには負けるわけにはいかない。自分が敗北すれば、多くの人々があの邪剣によって傷つくかもしれない。師と開祖の信頼に背くことにもなる。スタークォーツの胸中では、これまでの人生の中で最も強い使命感が宿っていた。